こんにちは、キョウです。
やる気に満ちて大きな目標を設定したのに、途中でうまくいかず、失敗してしまって落ち込んでいる—そんな状態になっていませんか?
「頑張って設定したのに、どうせ私には無理なんだ」と、すべてを諦めてしまうのは非常にもったいないことです。目標達成の道のりにおいて、失敗や挫折は設定ミスではなく、成長のサインです。
この記事では、目標達成に失敗して心が折れてしまった時、「続ける」か「再設定する」かを判断するための具体的な基準と、もう一度立ち上がるための方法をご紹介します。
なぜ目標達成に失敗すると深く落ち込んでしまうのか?
目標を設定したにも関わらず失敗すると、私たちは「目標が大きすぎた」という以上に、精神的なダメージを負ってしまいます。
失敗を「自己否定」と結びつけるから
- 目標未達成を自分の価値と同一視する
- 目標達成に失敗すると、「目標が達成できなかった」事実だけでなく、「自分には能力がない」「頑張りが足りない」と、目標と自分自身の価値を結びつけて考えてしまいがちです。これが、深い落ち込みの理由になります。
完璧主義の罠にはまっているから
- 一度設定した目標は完璧に達成すべきと考える
- 一度設定した目標は、完璧に達成しなければならないというプレッシャーが、失敗したときのダメージを大きくします。「少しでも遅れたら終わり」という考え方が、目標を継続する上で最大の敵となります。
「過程」ではなく「結果」だけを評価するから
- 努力や成長を見落としてしまう
- 目標設定した時点から、「達成」という結果のみに意識が集中していると、そこに至るまでの小さな努力や成長を見落としてしまいます。結果が出ないと、すべての努力が無価値だったと感じてしまい、落ち込みが深くなります。

心が折れた時、目標を続けるか見直すか?決断を下す3つの基準
目標達成に失敗し、モチベーションが著しく低下したとき、感情ではなく、客観的な事実に基づいて決断を下すための基準を持ちましょう。
1. 本当に大切にしたいこと(あなたの価値観)と一致しているか?
目標設定時と比べて、その目標が現在、あなたが本当に大切にしたい「価値観」とまだ一致しているかを確認します。
価値観の根本を再確認する
- 目標の土台をチェックする
- 当時、その目標を設定した根本的な理由を思い出し、現在の自分がより重視する価値観(例:会社の昇進)と目標が衝突しているなら、見直しの基準となります。
義務感で続けていないかを問う
- 目標を誰のために追っているか確認する
- その目標が「誰か」への見栄や期待に応えるための「義務感」になっていないかを問い直します。純粋に自分の幸福に繋がらない目標であれば、見直す方が賢明です。
2. 達成に必要な「リソース」は現実的に確保できるか?
情熱があっても、現実的なリソース(資源)が不足していては、目標達成は困難です。確保できるか否かを客観的に判断します。
「時間」と「資金」の確保を見直す
- 必要なリソースの現在と未来の確保可能性を評価する
- 目標達成に必要な残り時間と資金を具体的に算出します。特に、目標設定後に(例:転職や家族構成の変化)などでリソースが大幅に減った場合、目標の見直しは現実的な対応となります。
スキルアップにかかる時間を再評価する
- 目標達成に必要なスキルレベルを現実的に評価する
- 自分のスキルや能力が、目標達成レベルに到達するまでに必要な「時間」と「努力」が、当初の想定よりも大幅に長いと判明した場合、リソース不足とみなし、目標を段階的に再設定する基準とします。
3. 「外部要因」が恒久的な足かせになっていないか?
個人の努力では変えられない外部環境が、目標達成を阻害していないかをチェックし、その問題が一時的か恒久的かを判断します。
外部要因が「一時的」か「恒久的」かを判断する
- 問題が外部環境によるものか自責かを分離する
- 失敗の理由が、自分の努力ではどうにもならない(例:市場の急な縮小や規制変更など)「外部要因」によるものであれば、目標自体を現状に合わせて見直す基準となります。一時的な問題であれば継続を検討します。
代替案の存在を確認する
- 目標達成の別ルートを探る
- 外部要因によって現在の方法が不可能になった場合、別のアプローチやルートで同じ価値にたどり着けるかを探ります。代替ルートが見つからない場合、目標を見直す理由になります。

目標を「失敗」させないための立て直し技術
再設定が必要だと判断した場合でも、すぐに別の目標を探す必要はありません。目標達成に失敗した経験を活かし、落ち込みから立ち直るための具体的な方法をご紹介します。
1. 目標を「スモールゴール」に再設定する
大きな目標を達成できなくても、自信を失わないように、目標の大きさを変えます。
「今日できること」に焦点を絞る
- 達成ハードルを意図的に下げる
- 目標設定を「最終的な結果」から「今日の行動」に変更します。(例:「1年で50万円貯金する」→「今週は1,000円だけ節約する」)。達成体験を積み重ねることで、自信を回復させます。
2. 「努力の進捗」を記録する
結果が出なくても、目標達成のために行った努力や行動を客観的に記録し、自分を承認します。
「頑張ったことリスト」を作る
- プロセスを価値あるものとして記録する
- 成果が出なくても「〇〇について調べた」「〇〇さんに相談した」など、目標に向けて行ったプロセスを記録します。これにより、失敗したとしても、自分の努力が無価値ではないことに気づけます。
3. 「休息」を目標の一部にする
心と体が疲弊しているときは、休息を目標達成を遠ざける失敗だと考えず、目標達成に不可欠なプロセスとして設定します。
休息を「回復という名のタスク」と捉える
- 休むことへの罪悪感を解消する
- 「今日は目標から離れて完全に休む」という項目をあえてスケジュールに組み込みます。これにより、休むことへの罪悪感が消え、目標再設定に向けてエネルギーを回復できます。

まとめ
目標設定に失敗して深く落ち込んでしまうのは、あなたがそれだけ真剣に、真正面から目標に向き合ってきた証拠です。まずはその頑張りと、今の落ち込んでいる自分自身を、まるごと認めてあげてください。
目標を「続ける」か「再設定する」かは、「価値観」「リソース」「外部要因」という3つの客観的な基準で判断し、必要であれば「スモールゴール」として目標を設定し直しましょう。
失敗した経験は、あなたの目標をより確実にするための貴重なデータです。この貴重なデータを活かして、次に進むためのヒントを見つけましょう。
今回ご紹介した中で、あなたが目標を再設定する際の判断基準として、特に重要だと感じたのはどの項目ですか?ぜひコメントで教えてくださいね。
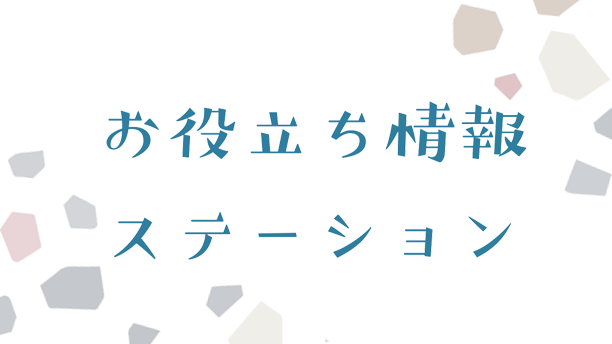









コメント