こんにちは、キョウです。
毎日、次から次へと降ってくるタスクをこなすことに追われ、気づけば本当にやりたいこと、将来のために大切なことが何もできていない…そんな状態に陥っていませんか?
何から手をつけたらいいか分からず、目の前の「緊急なこと」ばかりに時間を奪われてしまうのは、優先順位の決め方に明確な基準がないことが原因です。
この記事では、仕事でもプライベートでも応用できる、本当に大切なことに集中するための優先順位の決め方と、判断するための基準をご紹介します。
なぜタスクに追われ、大切なことが後回しになるのか?
日々タスクに埋もれてしまうのは、私たちが「重要ではないが緊急なこと」に反射的に反応してしまう人間の習性によるものです。
緊急なタスクを優先してしまうから
- 電話の着信やチャットの通知など、緊急性のあるタスクはすぐに手をつけたくなるものです。しかし、これらは必ずしも「重要」ではありません。緊急度に引きずられ、本当に大切なタスクが常に後回しになってしまいます。
タスクの「全体像」が見えていないから
- タスクリストが雑然としていると、一つ一つのタスクの重みや、それが将来につながるかどうかの判断ができなくなります。その結果、目についたものから順に処理するという非効率な決め方になってしまいます。
「完璧主義」が邪魔をするから
- 小さなタスクでも完璧に仕上げようと時間をかけすぎた結果、時間がすべてなくなり、大きな重要タスクに取り組む体力が残らない、という悪循環に陥ってしまいます。
優先順位の決め方を変える:4つの箱の活用
タスクの優先順位を決める最も強力な基準の一つが、「重要度」と「緊急度」の2軸でタスクを分類する「アイゼンハワー・マトリクス(4つの箱)」です。
このマトリクスを使って、優先順位を明確にしましょう。

最優先:重要かつ緊急なタスク
- 概要:すぐに対処すべき危機的なタスク
- 例:締切直前のプロジェクト、発生したクレームへの対応。できるだけ減らすことを目指します。
第二優先:重要だが緊急ではないタスク
- 概要:最も時間を割くべき「大切なこと」
- 例:スキルアップのための勉強、健康維持、人間関係の構築。ここに集中することが、将来の成功につながる鍵です。
第三優先:重要ではないが緊急なタスク
- 概要:他人を頼って任せる(委任する)べきタスク
- 例:すぐに対応が必要な電話やメール、定期的なルーティン作業。他人やツールに任せる基準を持ちましょう。
削除対象:重要でも緊急でもないタスク
- 概要:極力手をつけないタスク
- 例:特に目的のないネットサーフィンやSNSチェック。このタスクを減らすことが、時間確保の第一歩です。
実行力を高めるための「基準」と「対策」3ステップ
第二優先(重要だが緊急ではないタスク)に集中し、タスクに追われる状態から脱却するための具体的な決め方と対策をご紹介します。
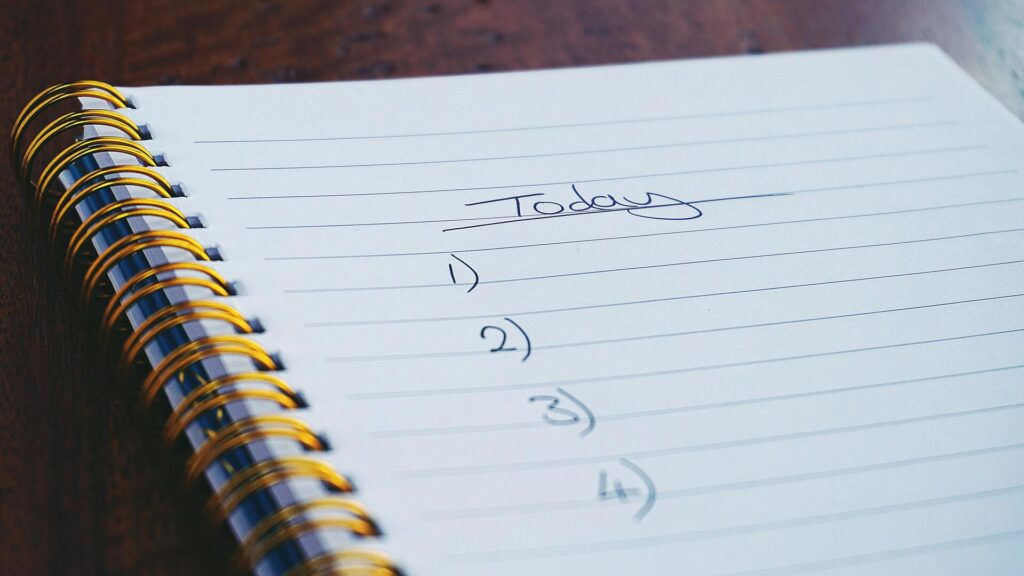
1. 「人生の目標」をタスクの基準にする
仕事やプライベートのタスクを、あなたの長期的な目標達成に繋がるかどうかという基準で判断します。
価値観に沿っているかチェックする
- 目の前のタスクが、「自分の成長」「家族との時間」「収入アップ」など、あなたが大切にする価値観に本当に貢献するかどうかを優先順位の基準にします。貢献しないものは、思い切って手放す決め方を選びましょう。
2. 「カエルを食べる」時間を確保する
作家マーク・トウェインの「朝一番に最も難しく、嫌なタスク(カエル)を片付ければ、その日一日、それより悪いことは起こらない」という言葉が由来。あなたの「カエル」(最も気が進まないが重要なタスク)を、毎朝最初に片付ける習慣をつけましょう。
朝一番に重要タスクに取り組む
- 脳の集中力が最も高い朝の時間帯に、最優先で「重要だが緊急ではないタスク」(第二優先)に取り組みます。これが成功すると、その日一日、達成感を持って過ごせます。
3. スケジュール帳に「守りの時間」を設定する
緊急タスクに割り込まれないよう、第二優先のタスクのための時間を物理的にブロックして確保します。
「ブロックアワー」を設定する
- 勉強や企画の立案など、集中が必要なタスクに対し、「10:00〜12:00はタスクA以外は対応しない」とスケジュール帳に書き込みます。この時間枠は、あなた自身が守るべき基準です。

まとめ
タスクに追われる毎日から脱却し、本当に大切なことに集中するためには、緊急度ではなく「重要度」を優先順位の決め方の基準に据えることが不可欠です。
今日から、目の前のタスクを「4つの箱」に分類し、第二優先のタスクに集中的に時間を使う対策を始めましょう。それが、あなたの仕事や人生の質を大きく向上させる一歩となります。
今回ご紹介した「優先順位の決め方」の中で、あなたが明日から試してみたい基準は何ですか?ぜひコメントで教えてくださいね。
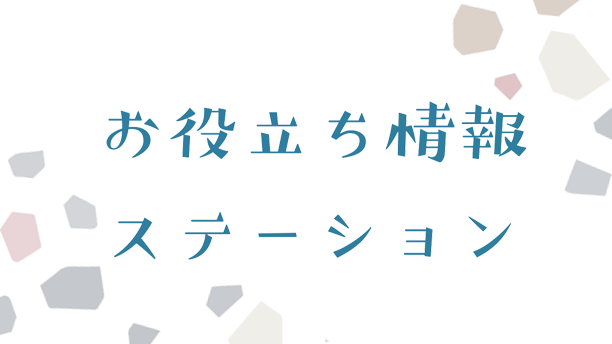









コメント