こんにちは、キョウです。
仕事中や日常生活で、予期せぬトラブルや、いますぐ解決しなければならない緊急なタスクが発生したとき、つい頭が真っ白になって焦る気持ちに支配されてしまうことはありませんか?
「早く何とかしなくては」と急ぎの気持ちばかりが先走り、かえってミスを増やしたり、冷静な対応ができなくなったりするのは、非常にもったいないことです。
この記事では、突然の急ぎの対応が必要になったときでも、焦ることなく、いつもの実力を発揮するための具体的なテクニックをご紹介します。
なぜ人は「急ぎの対応」で焦ってしまうのか?
突然のトラブルに対して焦るのは、あなたの意志が弱いからではなく、人間の脳が持つ「闘争・逃走反応」が関係しています。
脳が「緊急事態」だと誤認識するから
- 予期せぬ出来事が発生すると、脳は生命の危機だと錯覚し、パニックモードに入ります。これにより、冷静な思考や論理的な判断を司る部分の機能が低下し、焦る気持ちが強くなります。
「時間がない」というプレッシャーが重なるから
- 早く対応しなければならないという急ぎの感情は、タスクの難易度以上にストレスを高めます。「失敗したらどうしよう」という不安が焦る気持ちを増幅させます。
思考が「点」で止まってしまうから
- 焦ると、問題全体を俯瞰(ふかん)できず、「この部分をどうにかしないと」という目の前の急ぎの作業だけに意識が集中します。その結果、最も効果的な対応の順序を見失ってしまいます。
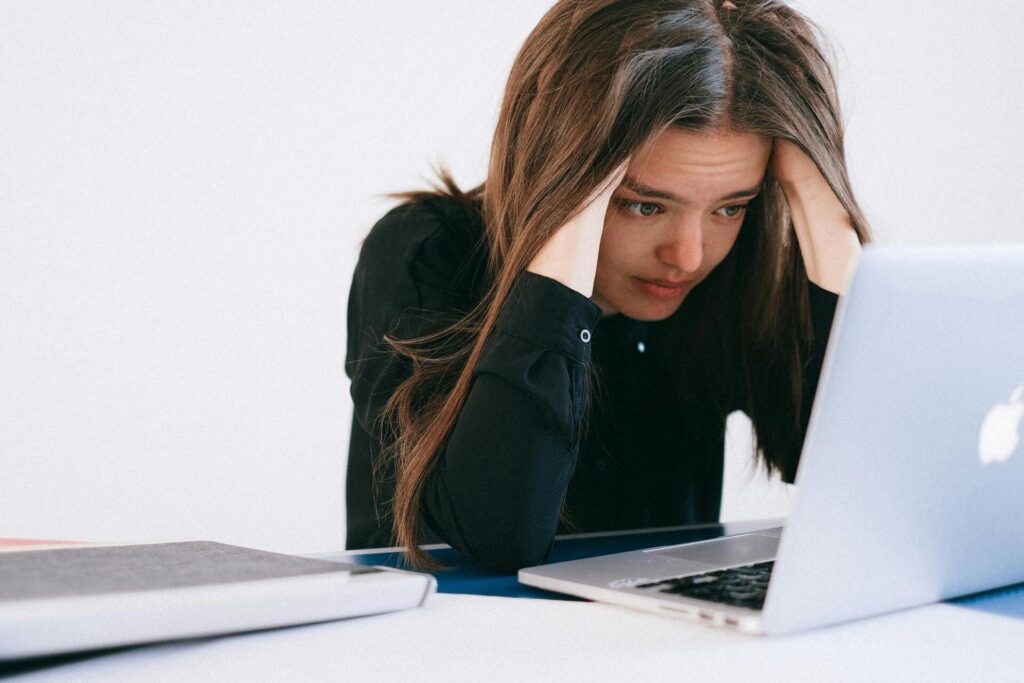
焦りを鎮め、平常心を取り戻すための3秒対応術
「焦る」感情を完全に消すことはできませんが、その初期衝動をコントロールすることは可能です。まずは3秒でできる冷静な対応術を身につけましょう。
3秒間「動作」を止める
- 急ぎの対応が必要だと感じた瞬間に、手を止め、口を閉じ、深呼吸をします。この3秒間の「停止」が、脳のパニックモードから抜け出すトリガーになります。
最初に「何が起きたか」だけを言葉にする
- 「どうしよう」と感情的な言葉を出す代わりに、「〇〇のシステムが止まった」「Aさんからの連絡が来ない」など、感情を交えずに客観的な事実のみを声に出して確認します。
「完璧」を求めず「最小の対応」を目標にする
- 焦るときは、すぐに問題を完璧に解決しようとしがちです。最初に「最悪の事態を防ぐための最小の対応は何か?」という基準を持ち、その一点に集中します。(例:クライアントへの報告、電源の再起動など)

急ぎの対応を成功させるための「タスク分解」技術
初期の焦る気持ちを乗り越えたら、次はその急ぎの対応を、普段通りのタスクとして処理できるよう「分解」します。
1. タスクを「事実」と「感情」に分解する
起きた事象を「対応すべき事実」と「自分が感じている焦り」に分け、感情的な要素を排除します。
事実:問題解決に必要な行動のみを抽出する
- 対応すべき事実:メールを送る、資料を確認する、上司に報告する。
- 焦る感情:どうしよう、私のせいだ、間に合わないかもしれない。
2. 「最初の10分」でできることをリストアップする
全体を見通そうとせず、この急ぎの対応のために「最初の10分で何ができるか」という小さな基準でタスクを区切ります。
10分後のゴールを設定する
- 例:対応のゴールが「資料の提出」であっても、10分後のゴールは「資料の該当ページを特定する」にします。目の前の10分に集中することで、焦る気持ちを鎮めます。
3. 「いつもの手順」に組み込む
急ぎの対応でも、普段の業務で使っている確認リストやテンプレートなど、慣れた手順に当てはめて処理します。
慣れた作業を対応の軸にする
- 電話対応であれば「相手の名前と要件をまず復唱する」、資料作成であれば「まず目次から作る」など、普段の習慣を急ぎの対応の土台にします。これにより、思考が自動的に平常モードに戻ります。

まとめ
突然の急ぎの対応に直面したとき、「焦るのは自然なこと」と認めつつ、3秒間の「停止」と「事実の言語化」で脳を冷静なモードに戻すことが大切です。
そして、問題を小さなタスクに分解し、普段の習慣というレールに乗せて処理することで、あなたは最高のパフォーマンスを発揮できます。
今回ご紹介した中で、あなたが次に急ぎの対応が必要になったときに試してみたい対策は何ですか?ぜひコメントで教えてくださいね。
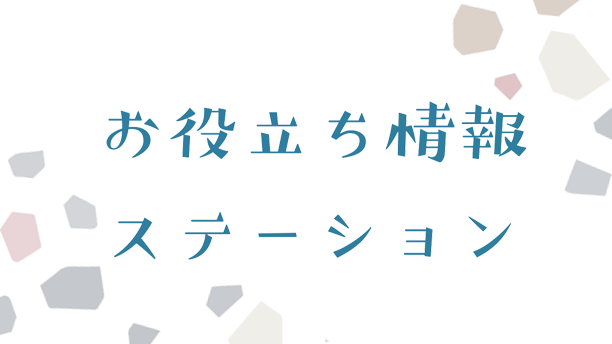









コメント